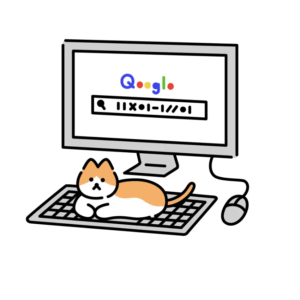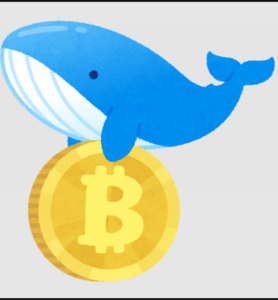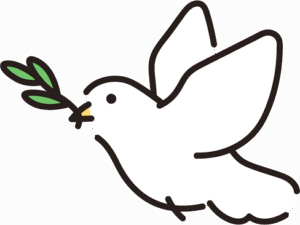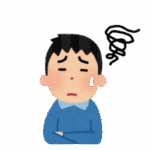
資産運用を始めたいけど、種類が多すぎてどれを選べばいいのかわからない…
本記事ではこんなお悩みを解決します。
✅ 本記事の内容
- 資産運用の種類10選をリスク別に徹底比較
- 初心者におすすめの資産運用3選
- 投資で失敗しないための5つの重要ポイント
✅ 本記事の信頼性
- 公務員×2児ママの40代
- iDeCo8年間の運用で+90%
- 18年間の資産運用で、もう少しでFIRE目標額達成!
この記事を読むと、自分に合った資産運用の種類が見つかり、今日から具体的に行動を始めるきっかけになると思います。
将来の経済的不安を解消したい、老後資金を準備したいという方はぜひ最後までご覧くださいね。
資産運用とは?初心者が知っておくべき基礎知識


資産運用とは、自分の持っているお金を預貯金や投資によって効率的に増やしていくことです。
ただ銀行に預けているだけでは、超低金利の現代ではほとんどお金は増えません。むしろインフレによって、お金の価値が相対的に減ってしまうリスクもあります・・・。
ここでは資産運用を始める前に知っておくべき基礎知識を解説していきますね。
資産運用の目的とメリット
資産運用の主な目的は、将来に向けて自分の資産を増やすことです。
具体的には以下のような目的があります。
- 教育資金の準備:子どもの進学費用を計画的に貯める
- 老後資金の準備:公的年金だけでは不安な老後生活に備える
- 住宅購入資金:マイホームの頭金や購入資金を準備する
- 生活の質向上:経済的余裕を持って豊かな生活を送る



資産運用には次のようなメリットがあります。
メリット1:預貯金より効率的に資産を増やせる
銀行の普通預金の金利は年0.001〜0.02%程度ですが、投資信託などで運用すれば年3〜5%程度のリターンを目指すことも可能です。
メリット2:インフレ対策になる
物価が上昇するインフレ時には、現金の価値が相対的に下がります。株式や不動産などの資産に投資することで、インフレに強い資産形成ができます。
メリット3:税制優遇制度を活用できる
NISAやiDeCoといった制度を利用すれば、運用益が非課税になったり、所得控除が受けられたりする税制メリットがあります。
資産運用で得られる利益は2種類(インカムゲイン・キャピタルゲイン)
資産運用で得られる利益には、大きく分けて2つの種類があります。
インカムゲイン(保有による利益)
金融商品を保有し続けることで、定期的に得られる利益のことです。
✅️具体例
- 預金の利息
- 株式の配当金
- 債券の利子
- 投資信託の分配金
- 不動産の家賃収入
インカムゲインは、資産を売却せずに継続的な収入を得られるのが特徴です。ただし、企業の業績や運用成果によって金額が変動したり、支払われない場合もあります。
キャピタルゲイン(売買による利益)
金融商品を購入したときよりも高い価格で売却することで得られる利益のことです。
✅️具体例
- 株式を安く買って高く売る
- 投資信託の基準価額が上がったときに売却
- 不動産を購入時より高く売却
- 外貨預金やFXの為替差益
キャピタルゲインは、インカムゲインよりも大きな利益を得られる可能性がある一方、損失(キャピタルロス)が発生するリスクも高くなります。
リスクとリターンの関係性を理解しよう
資産運用において最も重要な考え方が「リスクとリターンの関係性」です。
リスクとは「危険」ではなく「価格の振れ幅」のこと。
投資におけるリスクは、「損をする可能性」だけを意味するのではありません。正確には「価格がどれだけ上下するか(変動するか)」という意味です。
- リスクが大きい=価格の上下が激しい
- リスクが小さい=価格の変動が穏やか



資産運用では、リスクとリターンは基本的に比例関係にあります。
- ハイリスク・ハイリターン:大きく増える可能性もあるが、大きく減る可能性もある
- ミドルリスク・ミドルリターン:適度な収益を目指し、リスクも中程度
- ローリスク・ローリターン:安定しているが、大きな収益は期待できない
重要なのは、「リスクゼロで高いリターンを得られる投資は存在しない」ということです。
自分の年齢、家族構成、収入状況、性格などを考慮して、どの程度のリスクなら受け入れられるか(リスク許容度)を把握することが、資産運用成功の第一歩ですよ。
資産運用の種類10選を徹底比較【一覧表付き】


資産運用には多くの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
ここでは代表的な資産運用10種類を、リスクとリターンのレベル別に詳しく解説します。自分の目的やリスク許容度に合った方法を見つけましょう。
【一覧比較表】資産運用の種類10選
| 種類 | リスク | リターン | 最低投資額目安 | 流動性 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 預貯金・定期預金 | 低 | 低 | 1円〜 | 高 | 元本保証あり |
| 個人向け国債 | 低 | 低 | 1万円〜 | 中 | 国が発行、安全性高い |
| 投資信託 | 中 | 中 | 100円〜 | 高 | 分散投資、プロが運用 |
| NISA | 中 | 中 | 100円〜 | 高 | 運用益非課税 |
| iDeCo | 中 | 中 | 5,000円〜 | 低 | 税制優遇、60歳まで引出し不可 |
| 株式投資 | 中〜高 | 中〜高 | 数万円〜 | 高 | 配当・優待あり |
| 債券投資 | 低〜中 | 低〜中 | 1万円〜 | 中 | 利子を定期的に受取り |
| 不動産投資 | 高 | 高 | 数百万円〜 | 低 | 家賃収入、物件が資産に |
| FX | 高 | 高 | 数千円〜 | 高 | レバレッジ利用可能 |
| 暗号資産 | 高 | 高 | 数百円〜 | 高 | 価格変動が激しい |
【ローリスク・ローリターン】預貯金・定期預金
特徴
銀行や信用金庫にお金を預けることも、れっきとした資産運用の一種です。
普通預金は自由に出し入れできる一方、定期預金は一定期間引き出しに制限がある代わりに、やや高めの金利が設定されています。
メリット
- 元本保証がある(預金保険制度で1金融機関あたり1,000万円+利息まで保護)
- いつでも引き出せる(普通預金の場合)
- 投資の知識が不要で誰でも始められる
- 手続きが簡単
デメリット
- 金利が極めて低い(年0.001〜0.02%程度)
- インフレに弱く、実質的な資産価値が目減りする可能性がある
- 大きく資産を増やすことは期待できない
こんな人におすすめ
- 近い将来使う予定のあるお金を安全に保管したい人
- 投資のリスクを一切取りたくない人
- 緊急時の生活資金を確保しておきたい人
【ローリスク・ローリターン】個人向け国債
特徴
国が発行する債券で、満期まで保有すれば元本と利息が受け取れます。
3年・5年(固定金利)、10年(変動金利)の3タイプがあり、1万円から購入可能です。
メリット
- 国が発行しているため安全性が非常に高い
- 最低金利保証があり(年0.05%)、銀行預金より有利
- 1年経過すれば中途解約も可能(一部利子の返還あり)
- 定期的に利子を受け取れる(年2回)
デメリット
- 1年間は換金できない
- 大きなリターンは期待できない
- 他の投資に比べて資金効率が低い
こんな人におすすめ
- 元本保証を重視しつつ、預金より少しでも高い利回りを求める人
- 1年以上使う予定のない余剰資金がある人
- 安全性を最優先に考える人
【ミドルリスク・ミドルリターン】投資信託
特徴
多くの投資家から集めたお金をまとめて、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに分散投資する金融商品です。
メリット
- 少額(100円〜)から始められる
- 専門家に運用を任せられるため、投資初心者でも取り組みやすい
- 1つの商品で複数の投資先に分散投資できる
- 毎月定額で自動積立ができる
- 海外の株式や債券にも手軽に投資できる
デメリット
- 購入時手数料、信託報酬(運用管理費用)などのコストがかかる
- 元本保証がなく、市場環境によっては損失が出る可能性がある
- 商品数が多く、選ぶのが難しい
こんな人におすすめ
- 投資の知識や経験が少ない初心者
- 分散投資でリスクを抑えたい人
- 少額からコツコツ積み立てたい人
- 銘柄選定や売買タイミングの判断が難しいと感じる人
【ミドルリスク・ミドルリターン】NISA(少額投資非課税制度)
特徴
NISAは投資で得た利益が非課税になる制度です。通常、投資の利益には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で運用すれば税金がゼロになります。
2024年から新NISA制度が始まり、年間投資枠360万円(成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円)、非課税保有限度額1,800万円、非課税期間が無期限になりました。
メリット
- 運用益や分配金が非課税(通常20.315%の税金がかからない)
- 少額(100円〜)から投資可能
- 成長投資枠とつみたて投資枠を併用できる
- いつでも売却・現金化できる
- 非課税期間が無期限
デメリット
- 元本保証はない(投資商品の価格変動リスクがある)
- 損失が出ても他の口座と損益通算できない
- 1人1口座しか開設できない
こんな人におすすめ
- 税制優遇を受けながら効率的に資産を増やしたい人
- 長期的に投資を続けられる人
- 教育資金、住宅購入資金、老後資金など様々な目的で資産形成したい人
【ミドルリスク・ミドルリターン】iDeCo(個人型確定拠出年金)
特徴
iDeCoは、自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選び、60歳以降に受け取る私的年金制度です。
メリット
- 掛金が全額所得控除となり、所得税・住民税が軽減される
- 運用益が非課税
- 受取時も税制優遇がある(退職所得控除・公的年金等控除)
- 月5,000円から始められる
- 強制的に老後資金を貯められる
デメリット
- 原則60歳まで引き出せない(流動性が低い)
- 加入時・運用時・受取時に手数料がかかる
- 掛金の上限が職業によって異なる(月1.2万円〜6.8万円)
- 元本割れのリスクがある(選ぶ商品による)
こんな人におすすめ
- 老後資金を確実に準備したい人
- 税制メリットを最大限活用したい人
- 60歳まで使う予定のない余剰資金がある人
- 自営業者やフリーランスで公的年金が少ない人
【ミドルリスク・ミドルリターン】株式投資
特徴
企業が発行する株式を購入し、株価の値上がり益(キャピタルゲイン)や配当金(インカムゲイン)、株主優待を得る投資方法です。
メリット
- 株価が大きく上昇すれば高いリターンが期待できる
- 配当金や株主優待を受け取れる企業もある
- 企業の成長を応援できる
- 売買のタイミングを自分で決められる
デメリット
- 株価が下落すれば損失が発生する
- 企業が倒産すれば株式の価値がゼロになる可能性がある
- 銘柄選定や売買タイミングの判断に専門知識が必要
- 1銘柄あたり数万円〜数十万円の資金が必要
こんな人におすすめ
- 投資の勉強をする時間と意欲がある人
- ある程度のリスクを取って高いリターンを狙いたい人
- 応援したい企業がある人
- 株主優待に魅力を感じる人
【ミドルリスク・ミドルリターン】債券投資(社債・外国債券)
特徴
企業や外国政府が発行する債券を購入し、定期的に利子を受け取り、満期には元本が返還される投資方法です。
メリット
- 定期的に利子を受け取れる
- 満期まで保有すれば元本が返ってくる(発行体が破綻しない限り)
- 株式より価格変動が小さい傾向にある
- 外国債券は日本より高い金利を得られる場合がある
デメリット
- 発行体が破綻すれば元本や利子が返ってこない可能性がある
- 満期前に売却すると元本割れする可能性がある
- 外国債券は為替変動リスクがある
- インフレに弱い
こんな人におすすめ
- 定期的な利子収入が欲しい人
- 株式よりも安定した投資をしたい人
- リスクを抑えつつ預金より高い利回りを求める人
【ハイリスク・ハイリターン】不動産投資
特徴
アパートやマンションなどの賃貸用不動産を購入し、家賃収入を得たり、物件を売却して利益を得る投資方法です。
メリット
- 毎月安定した家賃収入(インカムゲイン)が得られる
- 不動産という実物資産が残る
- インフレに強い
- ローンを利用すれば少ない自己資金でも始められる
- 生命保険代わりになる(団体信用生命保険)
- 相続税対策になる
デメリット
- 初期費用が高額(数百万円〜数千万円)
- 空室リスク、家賃下落リスクがある
- 地震や火災などの災害リスクがある
- 流動性が低く、すぐに現金化できない
- 物件管理の手間やコストがかかる
こんな人におすすめ
- 長期的に安定した収入を得たい人
- ある程度の初期投資ができる人
- 実物資産を保有したい人
- 不動産や税金に関する知識を学ぶ意欲がある人
【ハイリスク・ハイリターン】FX(外国為替証拠金取引)
特徴
2つの通貨(例:米ドルと日本円)の為替レートの変動を利用して利益を得る取引です。レバレッジを使えば、少額の資金で大きな金額を取引できます。
メリット
- 少額の資金で大きな取引ができる(レバレッジ最大25倍)
- 24時間取引可能
- 円高でも円安でも利益を狙える
- 為替手数料が外貨預金より安い
デメリット
- レバレッジにより大きな損失を被る可能性がある
- 為替相場が急変すると証拠金以上の損失が出ることもある
- 常に相場を監視する必要がある
- 精神的な負担が大きい
こんな人におすすめ
- 為替や経済に関する知識がある人
- 短期的な取引に時間を割ける人
- ハイリスク・ハイリターンを理解して受け入れられる人
初心者には基本的におすすめできません
【ハイリスク・ハイリターン】暗号資産(仮想通貨)
特徴
ビットコインやイーサリアムなどのデジタル通貨に投資する方法です。インターネット上でのみ存在する通貨で、価格変動が非常に激しいのが特徴です。
メリット
- 短期間で大きな利益を得られる可能性がある
- 少額(数百円〜)から投資できる
- 24時間365日取引可能
- 新しい技術への投資という側面がある
デメリット
- 価格変動が極めて激しい(数日で価値が半減することもある)
- ハッキングや取引所の破綻リスクがある
- 法規制の変更リスクがある
- 将来的に価値がゼロになる可能性もある
- 預金保険のような保護制度がない
こんな人におすすめ
- 新しい技術に興味がある人
- 余剰資金の一部で投機的な投資をしたい人
- 短期的な大きな価格変動を許容できる人



変動が激しいので、初心者には基本的におすすめできません!
初心者におすすめの資産運用の種類3選


資産運用の種類は多くありますが、初心者がいきなり複雑な投資を始めるのはリスクが高すぎます。
ここでは、投資初心者でも始めやすく、リスクを抑えながら効率的に資産形成できる3つの方法を厳選して紹介します。
①NISA|税制優遇で少額から始められる
NISAは投資初心者に最もおすすめできる制度です。
その理由は、運用益が非課税になるという大きな税制メリットがありながら、少額(100円〜)から始められ、いつでも売却できる柔軟性があるからです。



通常の投資では、利益に対して20.315%の税金がかかります。
例えば10万円の利益が出ても、約2万円が税金で引かれて手元に残るのは約8万円です。しかしNISA口座なら10万円がそのまま受け取れます。
✅具体的な始め方
- 証券会社や銀行でNISA口座を開設する
- つみたて投資枠か成長投資枠を選ぶ(または併用)
- 投資する商品(投資信託や株式)を選ぶ
- 毎月の積立額を設定する(100円〜可能)
- あとは自動で積み立てられる
✅初心者向けのポイント
まずは「つみたて投資枠」から始めるのがおすすめです。
つみたて投資枠の対象商品は、金融庁が厳選した長期・分散・積立投資に適した投資信託に限定されているため、初心者でも安心して選べます。
月1万円からでも十分です。無理のない金額で長期間続けることが、資産形成の近道です。
②投資信託|プロに運用を任せてリスク分散
投資信託は、運用のプロに任せられるため、投資の知識や経験が少ない初心者でも始めやすい方法です。
1つの投資信託を購入するだけで、国内外の数十〜数百の株式や債券に分散投資できるため、リスクも分散されます。
個別株を買うには1銘柄あたり数万円〜数十万円必要ですが、投資信託なら100円から購入できるのも大きな魅力です。
✅具体的な始め方
- 証券会社や銀行で口座を開設する(NISA口座との併用も可能)
- 投資する投資信託を選ぶ
- 購入方法を選ぶ(一括購入 or 積立購入)
- 購入金額を決めて発注する
✅初心者向けのポイント
投資信託を選ぶときは、以下のポイントを確認しましょう。
- インデックスファンドを選ぶ:市場全体の動きに連動するため、わかりやすく手数料も安い
- 信託報酬(運用コスト)が低いものを選ぶ:年0.1〜0.5%程度のものがおすすめ
- 純資産総額が大きいものを選ぶ:100億円以上が目安
- 積立購入にする:ドルコスト平均法でリスクを抑えられる
おすすめは「全世界株式インデックスファンド」や「米国株式インデックスファンド」です。



世界や米国の経済成長を取り込みながら、手数料を抑えて運用できます。
③iDeCo|老後資金の準備に最適
iDeCoは、老後資金を準備したい人にとって最強の制度です。
3つの税制メリット(掛金の所得控除、運用益非課税、受取時の控除)があり、節税しながら効率的に資産を増やせます。



特に掛金が全額所得控除になるのは大きなメリットです。
例えば、年収400万円の人が月2万円(年24万円)をiDeCoに拠出すると、年間約3.6万円の税金が軽減されます。
✅具体的な始め方
- 金融機関を選んでiDeCo口座を開設する
- 毎月の掛金額を決める(5,000円〜上限額まで)
- 運用商品を選ぶ(定期預金、保険、投資信託から選択)
- 自動で掛金が引き落とされ、運用開始
✅初心者向けのポイント
iDeCoの最大の注意点は「原則60歳まで引き出せない」ことです。そのため、以下のポイントを押さえて始めましょう。
- 無理のない掛金額から始める:生活に支障が出ない範囲で設定
- まずは月5,000円から:あとから増額も可能
- 元本確保型商品も選択肢に:リスクを取りたくない人は定期預金も選べる
- NISAと併用する:両方活用することで税制メリットを最大化
iDeCoは長期投資が前提なので、20代〜50代前半で始めるのが最も効果的です。
資産運用で失敗しないための5つのポイント
資産運用を始めても、間違った方法で続けると失敗のリスクが高まります。
ここでは、初心者が資産運用で失敗しないために押さえておくべき5つの重要ポイントを解説します。


余裕資金で始める(生活費は確保する)
資産運用は必ず余裕資金で行いましょう。



生活費や近い将来使う予定のあるお金まで投資に回してしまうと、急な出費があったときに困ります。
さらに、相場が下落したタイミングで無理やり売却せざるを得なくなり、損失が確定してしまうリスクがあります。
✅具体的な対策
- 生活防衛資金を確保する:生活費の6ヶ月〜1年分を普通預金や定期預金で確保
- 使う予定が決まっているお金を分ける:住宅購入、教育費など3〜5年以内に使う予定のお金
- 余剰資金を投資に回す:上記以外の「当面使う予定のないお金」だけを投資する
例えば、手取り月収25万円の人なら、生活防衛資金として150万円〜300万円を預貯金で持っておき、それ以外の余剰資金で投資を始めるのが理想的です。
分散投資でリスクを抑える
「卵を一つのカゴに盛るな」という投資の格言があります。
1つの投資先に集中すると、その投資先が大きく下落したときに資産全体が大きく減ってしまいます。
複数の投資先に分散することで、リスクを抑えながら安定したリターンを目指せます。
✅具体的な分散方法
1. 資産の分散
- 株式、債券、不動産(REIT)、金など異なる資産に分散
- 値動きの特徴が異なる資産を組み合わせることでリスク軽減
2. 地域の分散
- 日本だけでなく、米国、欧州、新興国など世界中に分散
- 1つの国の経済が悪化しても、他の地域でカバーできる
3. 時間の分散(ドルコスト平均法)
- 一度に大金を投資せず、毎月定額で積み立てる
- 価格が高いときは少なく、安いときは多く買える
- 平均購入単価を抑える効果がある
初心者は、「全世界株式インデックスファンド」1本に毎月積立投資するだけで、上記3つの分散がすべて実現できます。



1つの商品で世界中の数千社に投資できるため、手軽に分散投資ができるのでオススメです🌏
長期投資を心がける
投資は短期間で見ると価格が大きく上下しますが、長期間保有することで安定したリターンが期待できます。
歴史的に見ても、世界経済は長期的には成長を続けています。
短期的な価格変動に一喜一憂せず、じっくり育てる姿勢が成功の鍵です。
✅長期投資のメリット
- 複利効果が得られる:運用益を再投資することで、雪だるま式に資産が増える
- 短期的な暴落を乗り越えられる:リーマンショックやコロナショックも長期で見れば回復している
- 売買回数が減り、手数料や税金を抑えられる
- 精神的な負担が少ない:日々の価格変動を気にしなくて済む
✅具体的な期間の目安
- 最低5年以上:短期的な変動リスクを軽減
- 理想は10年〜20年以上:複利効果を最大限に活かせる
- 老後資金なら30年以上:若いうちから始めるほど有利
例えば、毎月3万円を年利5%で20年間積み立てると、元本720万円が約1,233万円に増える計算です(手数料・税金を考慮せず)。



これが複利の力です❤️
手数料やコストを確認する
投資には様々な手数料がかかります。
手数料は確実に利益を減らす要因なので、できるだけ低コストの商品を選ぶことが重要です。
特に長期投資では、わずかな手数料の差が最終的な資産額に大きな影響を与えます。
✅主な手数料の種類
投資信託の場合
- 購入時手数料:購入時に1回だけかかる(ノーロード商品なら無料)
- 信託報酬:保有期間中ずっとかかる年間コスト(年0.1〜2%程度)
- 信託財産留保額:売却時にかかる手数料(かからない商品も多い)
その他の手数料
- 口座管理手数料:証券口座の維持費(多くのネット証券は無料)
- 売買手数料:株式などを売買する際の手数料
- 為替手数料:外貨建て商品の場合
コスト削減のポイント
- ネット証券を選ぶ:店舗型証券会社より手数料が圧倒的に安い
- インデックスファンドを選ぶ:信託報酬が年0.1〜0.5%程度と低コスト
- NISA口座を活用する:運用益が非課税なので実質的なコスト削減になる



例えば、信託報酬が年1%と年0.2%の商品を比較すると、30年間で最終資産額に数百万円の差が出ることもあります!
定期的に運用状況を見直す
一度投資を始めたら完全に放置するのではなく、定期的に運用状況を確認し、必要に応じて見直すことが大切です。
ライフステージの変化や市場環境の変化によって、最適な資産配分は変わってくるからです。
✅見直しのタイミング
- 年に1〜2回:資産配分のバランスを確認
- ライフイベント発生時:結婚、出産、転職、住宅購入など
- 目標達成時:当初の目標金額に到達したとき
- 大きな市場変動時:リーマンショック級の暴落があったとき
✅具体的な見直し内容
1. リバランス(資産配分の調整)
当初「株式50%、債券50%」で始めたとしても、株価が上昇すると「株式70%、債券30%」のようにバランスが崩れます。定期的に売買して元の配分に戻す作業が「リバランス」です。
2. 積立額の見直し
収入が増えたら積立額を増やす、逆に支出が増えたら減らすなど、生活状況に合わせて調整します。
3. 商品の見直し
より低コストな商品が出てきたら乗り換えを検討する、投資方針が変わったら商品を変更するなどの判断をします。
注意点



ただし、短期的な価格変動で慌てて売買するのは避けましょう。
「見直し」と「狼狽売り」は別物です。あくまで冷静に、計画的に調整することが大切です。
まとめ
資産運用には預貯金から株式投資、不動産投資まで様々な種類があり、それぞれリスクとリターンの度合いが異なります。
✅初心者におすすめの投資
- NISA
- 投資信託
- iDeCo
これらは少額から始められ、税制優遇も受けられるため、効率的に資産形成ができます。
そして資産運用で失敗しないためには、余裕資金で始めること、分散投資でリスクを抑えること、長期投資を心がけることが大切です。手数料を確認し、定期的に運用状況を見直すことも忘れないようにしましょう。
資産運用は「いつか始めよう」と思っているだけでは、時間だけが過ぎてしまいます。
将来の経済的不安を解消し、ゆとりある生活を送るためには、早く始めることが何より大切です。「完璧な知識を身につけてから」ではなく、「まず少額で始めながら学ぶ」姿勢が成功への近道です。
この記事で学んだ知識を活かして、今日から資産運用の第一歩を踏み出しましょう。
あなたの将来がより豊かになることを願っています。