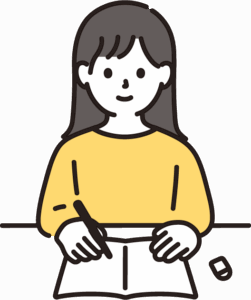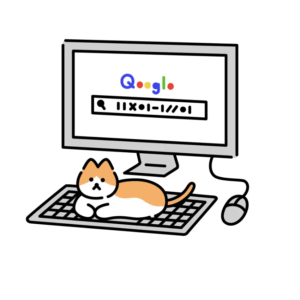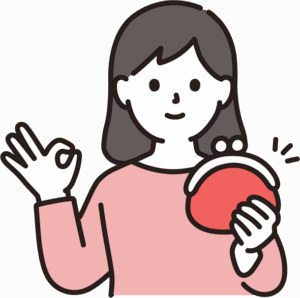教育費、住宅ローン、車の維持費…子育て世代の公務員にとって、家計のやりくりは本当に大変ですよね。
「FIRE(早期リタイア)を目指したいけれど、今の収入で本当にできるの?」
「どんな支出を見直せばいいのかわからない…」
そんな悩みを抱えている30代の子持ち公務員の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、こんなお悩みを解決します。
✅ 本記事の内容
・FIREを目指す子持ち公務員が家計簿をつけるべき理由
・平均年収ベースで見るリアル家計簿と支出割合
・固定費・教育費・通信費などの最適な見直しポイント
✅ 本記事の信頼性
・筆者は母子家庭育ちで、幼少期から節約体質が身についている現役公務員
・筆者は公務員、夫は民間勤務(公務員と同程度の収入)子供2人ありで、家計最適化中
・投資歴15年以上、資産を4.5倍に増やした経験をもとに執筆
この記事を読むと、FIREを現実的な目標として目指すために、「子持ち公務員がどこを見直せば家計が最適化できるのか」がわかります。
家計簿のつけ方や節約の優先順位、支出バランスを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
子持ち公務員がFIREを目指すなら家計簿が最重要な理由
FIRE(経済的自立・早期リタイア)を目指すうえで、家計簿は最も基本で、最も効果的なツールです。
なぜなら、「どこにお金を使っているか」を把握できないと、いくら節約しても資産は増えないからです。
家計管理ができないとFIREは実現しない

FIREに必要なのは「収入」よりも「支出のコントロール力」です。
いくら年収があっても、使い方を誤れば資産は増えません。
逆に、平均的な収入でも、支出を整えればFIREはぐっと現実的になります。
私は母子家庭育ちで、もともと節約体質。
結婚当初から「支出計画」を立てて、それに沿ってお金を使っていました。
でも、子どもが生まれてからは支出が増え、さらに「家計管理の重要性」を痛感。
特に育休明け、保育料が高くて本当にしんどかった時期がありました。
あの頃は「どこを削ればいいのかわからない」状態。
でも、家計簿をつけてみると、意外と食費・日用品・通信費の中に“ムダ”が多いことに気づいたんです。
そこから、「把握する」から「最適化する」に意識を変えました。
家計簿の目的は「把握」ではなく「最適化」
家計簿は“つけること”が目的ではありません。
本当の目的は「支出を最適化して、自分らしいお金の使い方を見つけること」。
たとえば私は、
- 食費は削りすぎない(子どもの健康やお弁当の質は大事)
- 体験にはお金を惜しまない(旅行・短期留学・家族時間)
- でも、固定費は徹底的に見直す(通信費・車・保険など)
このように、「何を大切にするか」を整理できるのが家計簿の本当の力です。
続かない公務員でもできる家計管理の始め方



家計簿が続かない理由は、“完璧にしようとするから”です。
🔹私の失敗談
最初は細かくレシートを全部入力していました。
でも、仕事・育児・家事をこなしながらでは無理…。
1ヶ月で挫折しました(笑)
🔹続けられた方法
今は銀行アプリとカード利用履歴を使って、ざっくり管理しています。
昔は月2回に分けて現金を下ろして「これしか使えない方式」で管理していたことも。
今はスマホで使用状況を確認できるから、アプリでざっくりでも十分。
私は最初「マネーフォワード」を使っていましたが、銀行連携が途中から合わなくなり、
今は「銀行アプリ+楽天カード2枚+ガソリンカード」で科目を分けて管理しています。
それぞれポイントがつくし、ガソリンも安くなります。
この方法だと、“どこにどれだけ使ったか”が一目でわかります。
家計簿は「FIREの土台」



家計簿は「節約のための面倒な作業」ではなく、
FIRE(自由な未来)を叶えるための最初の一歩。
“使うお金”を自分の価値観で選べるようになった瞬間、家計簿は「窮屈な管理」から「自由を広げるツール」に変わります。
子持ち公務員のリアル家計簿(支出割合)
FIREを目指すなら、「どこにどれだけ使っているか」を明確にするのが第一歩。
ここでは、子育て中の公務員家庭がどんな支出バランスで暮らしているのか、リアルな実例をもとに紹介します。
夫婦公務員×子育て世帯の支出割合
私の家庭は「公務員の私+会社員の夫」で、収入はほぼ同程度。
一般的な共働き公務員家庭と近いと思います。



ざっくりとした支出割合はこんな感じです👇
| 項目 | 割合(目安) | コメント |
|---|---|---|
| 食費 | 約17〜18% | 子どもの健康とお弁当を大切に。節約より“食の満足度”重視。 |
| 住居費 | 約12% | 住宅ローンは繰上げより条件最適化派。無理ない返済計画。 |
| 教育費 | 約20% | 塾代が高め。けど「投資」と割り切っている。 |
| 光熱費・通信費 | 約8% | 通信費は格安SIMで圧縮。電気代も契約プラン見直し。 |
| 車関連 | 約10% | 3年落ち中古車を狙って購入。台数・維持費を最適化。 |
| 保険 | 約6% | 必要最小限。学資保険は吟味して10年で払込完了。 |
| その他(レジャー・雑費など) | 約10% | 旅行・体験には惜しまず使う。家族の時間を重視。 |
| 貯蓄・投資 | 約15% | 先取り貯蓄+インデックス&個別株運用。 |



また、ボーナスは、住宅ローン返済、旅行費の不足分に使用し、残ったら投資に回すようにしています。
平均的な公務員家庭との比較
一般的な公務員家庭の平均支出と比べると、私の家計は少し特徴があります。
- 食費:やや高め(外食は少ないけど、食材の質とお弁当重視)
- 教育費:高め(塾代や短期留学など、経験への投資が多い)
- 通信費:かなり低め(格安SIM・ネット契約見直しで年間10万円近く削減)
- レジャー費:使うときは使う(旅行や体験は“節約対象外”)
私は「何でも節約」ではなく、
“使うところには使う、削るところは徹底的に削る”という考え方でバランスを取っています。
理想の支出バランス(FIRE視点での最適割合)
FIREを目指すなら、理想的な支出バランスはこんなイメージ👇
| 項目 | 理想割合 | ポイント |
|---|---|---|
| 生活費(食・光熱・通信など) | 50%以内 | 家計の半分で暮らせる体質づくり。 |
| 教育費 | 15〜20% | 投資と考える。ただし“青天井”にはしない。 |
| 住宅費 | 10〜15% | 固定費を圧迫しないローン計画。 |
| 車関連 | 5〜10% | 所有台数を見直すだけでも大幅改善。 |
| 貯蓄・投資 | 20〜25% | ここがFIREの原動力! |



FIREは「収入を増やす」よりも、
“固定費を最適化して投資に回す比率を上げること”が近道です。
数字以上に大切なのは「納得感」
家計のバランスを整えるうえで一番大切なのは、「自分が納得しているか」だと思います。
私も最初は節約ばかり意識してストレスが溜まり、
「なんのために頑張ってるんだろう」と思ったことがありました。
でも、「子どもとの旅行」「おいしい手作りごはん」「学びのための支出」など、
自分の価値観に沿った使い方を大切にするようになってから、お金の流れに満足できるようになりました。
リアル家計簿は“価値観の写し鏡”
FIREを目指すなら、家計簿は“節約ノート”ではなく、
「自分と家族の価値観を可視化するツール」として使うのがおすすめ。
数字のバランスも大事だけど、
「何にいくら使ったか」よりも「なぜそれを使ったか」を意識することで、
自然とムダが減り、貯蓄率も上がっていきます。
まず見直すべき支出3つ(固定費編)
FIREを目指すなら、まず固定費の最適化から始めるのが鉄則です。
支出のうち大きな割合を占める固定費を整えることで、毎月の余裕資金が大きく増え、投資や貯蓄に回せるお金が増えます。
我が家も最初は「節約って何から手をつけたらいいの?」という状態でしたが、固定費の見直しから取り組むことで、自然と家計に余裕が生まれました。
体験談も交えて具体的に紹介します。
通信費(格安SIM・乗り換え体験談)
通信費は毎月かかる固定費の中でも見直しやすく、削減効果が大きい項目です。
- 昔は大手キャリアで契約していて、家族4人で毎月約3万円近く(6,500円×4)かかっていました。
- 格安SIMに乗り換えた結果、家族4人で13,000円(4,000円×3+290円)まで圧縮できました。
- ahamoに乗り換え時にはキャンペーンを活用し、ドコモポイント2万ポイントをゲット。
- 娘だけはほとんど携帯をつかわわないので、日本通信の一番安いプラン(1ギガ月290円)にしています。
住宅ローン(繰上げ返済より条件最適化)
ローンは無理に繰上げ返済するより、条件の最適化を優先した方が賢明です。
- 我が家は15年前に変動金利で住宅ローンを組み、当初は35年返済の予定でした。しかし、「少しでも返済期間を短く」と思い、35年ではなく31年に計画変更。
- 当時15年固定1.35%で借りていましたが、返済途中(4年目)で銀行に相談し、「借り換えしようと思っている」と伝えたところ、低金利プランを提示されたので変動金利0.75%を選択し、借り換えはしないことに。
団信が付いているため、安心して毎月返済しています。 - 繰上げ返済を急ぐ必要はなく、金利と返済条件の見直しで固定費を抑えることができました。
- 金利が下がったことで、毎月の支出に余裕が生まれ、子どもとの旅行や短期留学費用も計画的に確保できました。
- 2025年現在は、金利がじわじわ上がってきているので、変動金利で借りている我が家は少し心配もあります。
車関連費(台数・買い方・維持費の考え方)
車は生活必需品ですが、購入や維持費で大きく支出を圧迫する可能性があります。
- 我が家は新車を買わず、3年落ちくらいまでのお買い得中古車を選んで購入。個人的に国産車は3年で4万〜5万キロ程度の過走行なら大丈夫だと思っています。
以前2年落ちのレクサス車が過走行5万キロで新車価格の半値で売っていたので即買いしたことがあります(中古車価格が値上がりする前ですが、東京のレクサスで購入しました。) - 車を1人1台必要とする地域なので、台数は減らせませんが、長く乗る・維持費を抑える方針で節約。
- タイヤは実店舗だと高いため、ネットで購入し整備工場に持ち込んで取り付けしている。(持ち込み料がかかることも…不安な方にはお勧めしませんが、今まで事前に問い合わせておけばトラブルはありませんでした。)
- 車を選ぶ際は、隣県まで足を運んでお買い得な車を購入することも。ただし、購入後のトラブルは販売店へ行って対応となることが多く、県外だと面倒ではあるので、よく考えてから購入を。
- 車検はディーラーで受けない。(安心感はありますが、見積もり15万〜30万と高い。私は、自分で見つけた安い老舗の車検工場にお願いしています(7年落ち車検で7万5千でした!)。)
- 車は生活に必須ですが、買い方と乗り方を工夫するだけで、年間数万円の節約になります。
固定費見直しで毎月の余裕を生む
通信費・住宅ローン・車関連費は、FIREに向けて最も効果的に削減できる固定費です。
我が家の体験を振り返ると、
- 通信費は格安SIMで大幅削減→月に17,000円節約し投資資金に
- 住宅ローンは金利交渉で条件最適化→返済額が5,000円軽減し投資資金に
- 車は中古車購入で維持費を抑制→浮いた分を投資資金に
これだけで毎月の余裕資金が増え、投資や貯蓄に回す原資が確保できます。
さらに、固定費の見直しは生活の安心感にもつながります。
「今月はこれくらい余裕がある」と目で見えることが、FIREに向けてのモチベーションアップにもなるんです。



ただし、頑張りすぎてストレスになっては元も子もありません。無理のない固定費見直しの方法を実践することをおすすめします。
教育費は“家計簿内で意識して管理”が正解
教育費は子育て世帯にとって大きな出費ですが、FIREを目指すなら生活費の中でしっかり意識して管理することが大切です。
家計簿上で教育費を無視したり、削りすぎると子どもの学びや体験の機会を制限してしまうことがあります。
ここでは、我が家の体験談を交えて具体的な管理方法を紹介します。
教育費は「生活費の一部」として把握する
- 家計簿内で教育費をカテゴリとして明確に分けて記録するだけでも十分把握可能。
- 毎月の支出に占める教育費を意識することで、使いすぎ防止と計画的支出ができます。
- このやり方で、旅行や体験費用も削らずに確保することができます。
塾・習い事を管理するコツ(スポット利用の考え方)
- 受験期以外はフル通塾はせず、夏期講習や無料体験だけ活用(もちろん本人が希望していれば受験期以外もフル通塾もOK!と思っています。)
- 夏期講習も可能な範囲で必要な教科だけスポット利用することで、費用を抑えつつ学力維持。
- 受験期は「将来への投資」と割り切って、必要な費用は惜しみなく使う。
- 家庭学習も本屋で子どもと参考書を選ぶなど工夫。
- この方法で、年間教育費をコントロールしつつ、子どもに必要な学びを提供できると考えます。
今考えると、中学1年の時、小学校時代と勉強の仕方が変わってどうやって勉強しよう!と子供達も悩んでいました。けれど、それを自分で考えて(私もアドバイスしましたが)乗り越えたことが、後になって活きていると感じます。
※目標成績は本人の進みたい進路から逆算。公立高の場合、上位10%が合格圏内の高校に進みたい場合一年時から上位20%には入っていないと後々厳しいでしょう。塾に通わなくても模試は受けられますので、現在の立ち位置を把握することが大切です。校内の成績だけで判断すると危険です。
塾で教えられることを淡々とこなせば、成績は一時的に伸びるとは思います。しかし、長い目で見ると「自分はどういうやり方が伸びるか」など、自分でわかっているた方が後で伸びる気がしています。
もちろん通える範囲に、そういったことも教えてくれる塾があれば一番助かるんですけどね(そしてその塾がリーズナブルなら言う事なし!←それが難しい😓)。
教育費を削りすぎない工夫
- 外国語体験や短期留学、家族旅行などは費用を惜しまない。
- 上の子は高2の夏休みにオーストラリア2週間短期留学(費用35万円)へ参加。
- 他にパスポート更新代やホームステイ先へのお土産代など雑費も発生。
- 下の子も希望があれば短期留学に参加予定。
- 節約のメリハリをつけることで、生活費と教育費のバランスが取りやすくなります。
家族旅行は、毎年夏休みに行っています。台湾、グアムなど比較的リーズナブルな海外から、国内は北海道1回沖縄2回、ミラコスタにも一回宿泊しました(高かった!)。
短期留学の際は、私の母が息子に現地で使う分のお小遣いをくれたので助かりました。
教育費は「把握とメリハリ」で管理
教育費を家計簿内で意識して管理することで、
- 削りすぎず、子どもの経験を確保できる
- 必要な学習投資を計画的に使える
- 生活費とのバランスがとれる



我が家の体験からも、教育費は家計簿内で把握し、使う時は使い、抑える時は抑えるメリハリ管理が、FIREを目指す子持ち家庭に最適な方法だと感じています。
家計簿が続かない公務員ママ・パパでも続くコツ
家計簿を続けるのは難しいと思っている方も多いですが、ポイントを押さえれば無理なく習慣化できます。
私自身、母子家庭育ちで節約体質とはいえ、仕事や育児で忙しい中、家計管理を継続するのは簡単ではありませんでした。
ここでは我が家のリアル体験を交えて、長続きのコツを紹介します。
完璧に管理しないのが長続きのコツ
- 最初から細かく全ての支出を記録しようとすると挫折します。
- 我が家では「大きな支出だけ把握」+「ざっくりカテゴリ管理」にしています。
- 食費や日用品、教育費など主要なカテゴリだけ毎月チェック。
- 削るところは削り、体験や子ども関係の支出は柔軟に調整。
- 例えば、旅行費や体験費は別枠で計画しておくことで、節約しつつ家族の楽しみを確保。
週1×10分で済ませる家計管理の仕組み
- 家計簿をつける日は週1回、10分だけ。
- 私はスマホのアプリ(マネーフォワードがお勧め!)と銀行アプリを組み合わせて管理しています。
- カード別管理でわかりやすく:ガソリンカード → ガソリン代のみ、通販用楽天カード → 食費・日用品など、街での買い物用楽天カード → 食費や雑費
- 週1回、アプリでサッと確認するだけで、何にいくら使ったか即座に把握可能。
- 余裕がある週は、先取り貯蓄や投資への振り分けも再チェックします。
挫折しないための“ズボラ向け習慣化”
- 家計簿は「毎日完璧に」ではなく「週1回まとめて」程度で続ける。
- 支出の多い月だけ詳細にチェックし、少ない月はざっくりでOK。
- 私自身、育児や仕事で忙しい時期は、簡単に管理できる方法に切り替えて継続。
- 食費や日用品の買い物の際に「今日は卵の日だ〜」と自然に体が動くようにする
- 旅行や短期留学など特別な出費は、事前に目標を立ててメリハリ管理
- 無理をしないことが、長期的なFIRE達成につながると実感しています。
この方法なら、家計簿が苦手な公務員ママ・パパでも自然に続けられると思います。
また、公務員のいいところに「安定したボーナス支給」があります。公務員の給料は、大企業などに比べると残念ながら決して高くありません。しかし、安定はしているためボーナスを予算に組み込んでいても、問題になることはほとんどありません。
毎月の給料だけでやりくりできない月もたまにはあると思います。そんな時はボーナスで補填し、しかしそれが当たり前にならないように、適度に管理するとストレスにならずに長く続けられると思います。
まとめ:FIREを目指す子持ち公務員の家計最適化
FIREを目指す子持ち公務員にとって、家計管理と支出の見直しは必須です。
本記事で紹介した内容を整理すると、無理なく支出をコントロールし、将来の資産形成につなげられます。
重要ポイント
- 家計簿を最重要ツールとして活用
- 支出の把握と最適化がFIRE達成の第一歩
- 完璧を目指さず、週1回10分で続けられる仕組みを作る
- 子持ち公務員のリアル家計を知る
- 平均年収ベースの支出割合を参考に、自分の家計を調整
- 食費や教育費は削りすぎず、体験や楽しみには適切に投資
- 固定費を重点的に見直す
- 通信費、住宅ローン、車関連費をチェック
- 借り換え交渉や中古車活用など、具体的体験談を参考にする
- 教育費はメリハリをつける
- 塾や習い事はスポット利用で管理
- 短期留学や旅行などの体験費は必要な分だけ確保
- 家計簿を続けるコツ
- カード別管理やアプリ活用で簡単チェック
- 無理せず、楽しみながら家計管理を習慣化
行動へのポイント
- 週1回、10分だけ家計簿を確認
- 固定費の無駄を見直す
- 教育費や体験費はメリハリをつける
- 家族で話し合いながら、継続できる仕組みを作る



これらを実践することで、子育てとFIRE準備を両立しながら、生活の質を保ちつつ資産形成が可能になります。
節約と投資をバランスよく行い、将来の自由な時間と安心を手に入れましょう。