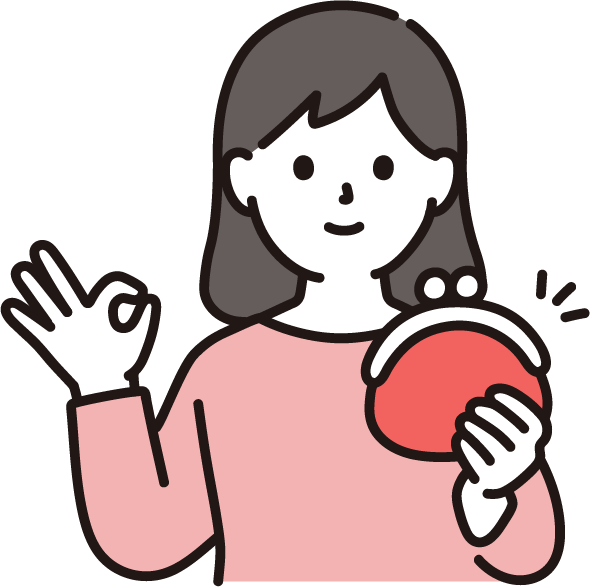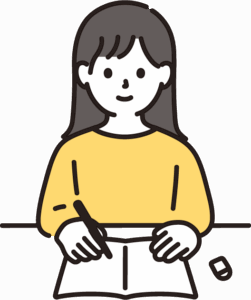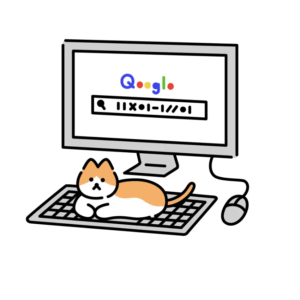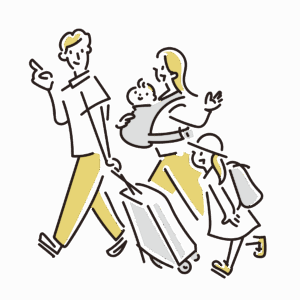子持ち公務員で、将来のFIREを目指したいけれど
「家計を見直しして最適化するには、どうやって節約すればいいの?」
と悩んでいませんか?
本記事では、そんなお悩みを解決します。
✅ 本記事の内容
- 節約・家計見直しで無理なく支出を最適化する方法
- 投資・資産運用で安定した資産形成をする方法
- 福利厚生や安定収入を活かして家族サービスも楽しむ方法
✅ 本記事の信頼性
- 筆者は実際に40代子持ち公務員で、福利厚生を活かしたレジャーや節約生活を実践
- iDeCoやNISAで資産運用を行い、資産増加(iDeCo9年で+90万)の実績あり
- 幼少期母子家庭で育ち、お金の不安から節約習慣が身についている
この記事を読むと、家計の無理ない見直し方・資産形成の方法・福利厚生の活用法がわかるので、
今すぐ自分の家計を整えてFIREに向けて一歩を踏み出すことができます。
FIREを目指す子持ち公務員の方はぜひ最後までご覧ください。
子持ち公務員がFIREを目指す前に知っておきたい家計最適化のポイント
公務員の安定した収入や福利厚生を活かせば、子育て世帯でも無理なくFIREを目指せます。
まずは家計の優先順位を整理して、効率よくお金を回すポイントを押さえましょう。
公務員がFIREを目指すメリット(安定収入・福利厚生)
公務員は、安定した収入と手厚い福利厚生があるため、FIRE(経済的自立・早期リタイア)を目指すにはとても有利です。
景気に左右されにくく収入が安定しているため、家計管理や資産形成の計画が立てやすいのが大きな強みです。
特に、毎月決まった収入があることは「積立投資」と相性抜群。
積立NISAやiDeCoなどは「長期間コツコツ続けるほどリターンが大きくなる投資」なので、給与が安定している公務員は成果が出やすい傾向があります。
また、公務員には各種手当、休暇制度、宿泊補助、医療・育児支援などの福利厚生も多く、家計に直結する“見えない収入”になります。
これらを上手に活用することで、支出を抑えながら資産形成に回せるお金を増やせるのがメリットです。
まず見直すべき家計の優先順位(固定費→変動費→教育費→投資)
FIREを目指すなら、やみくもに節約するのではなく、正しい順番で家計を整えることがポイントです。
- 固定費の見直し
住宅費・保険料・通信費など、毎月必ずかかる費用を最適化。
ここが下がると節約効果が長続きします。 - 変動費の節約
食費・日用品・レジャーなど、生活の質を落とさずに節約する工夫を取り入れる。 - 教育費の計画
子どもの教育費は大きな支出。
塾はフル活用ではなく“スポット利用”や“成績に応じて最適化”するのがカギ。 - 投資をスタート
iDeCo・NISAなどで将来の資産形成。
固定費と教育費を整えた上で、無理のない額から始める。
この順序で見直すことで、無理のない節約と効率的な資産形成が同時に叶います。
子育て世帯でも家計最適化が可能な理由
「子どもがいると節約は難しい…」と思われがちですが、工夫次第で家計最適化は十分可能です。
子育て世帯は支出が増える反面、公務員ならではの制度や地域サービスを組み合わせると、大きく節約できます。
- 食費は無人販売所やふるさと納税をフル活用
- 日用品や衣類は100均・セール・ポイントでお得に購入
- 通信費は格安SIMや乗り換えキャンペーンで年間数万円削減
- 公務員の福利厚生でレジャー・宿泊費・保険料を節約
上記について、次からの章で詳しく説明していきます。
 茶ぴ子
茶ぴ子私自身も子ども2人の家庭ですが、こうした工夫を取り入れることで、我慢しない節約を続けられています。
「節約=頑張るもの」ではなく、仕組み化して勝手に節約される状態を作るのがポイントです。
子持ち公務員の節約&家計見直し術
日々の生活でできる小さな工夫が、家計最適化の大きな力になります。
食費や日用品、通信費など、無理なく節約できる方法を具体的にご紹介します。
食費の節約術(無人販売所・ふるさと納税・買い物の工夫)
子育て世帯の大きな出費のひとつが食費です。
私も最初は「どうやって節約したらいいの…?」と悩みましたが、少し工夫するだけで無理なく抑えられます。
例えば、道端にある無人の野菜販売所を3箇所ほど行きつけにしています。(私の住む地域は結構あります)
無人なので箱にお金を入れていくシステム。お釣りなく払えるよう、大根100円きゅうり•なす1袋100円といった価格設定になっています。旬の野菜が安く手に入り、新鮮でおいしいので、子どもたちも喜びます。
また、実家が農家という同僚からのご厚意で、コメや野菜を安く購入したり、ふるさと納税で玉ねぎや肉をもらうこともあります。
これだけでも、毎月の食費はかなり抑えられています。
買い物の際は、スーパーのポイント5倍デーや閉店前の半額セールも活用しています。
最初は少し面倒に感じますが、慣れると「今日は卵の日だ!」と自然に動けるようになりました。
こうしたちょっとした工夫が積み重なって、家計最適化につながります。
日用品・衣類の節約術(100均・ユニクロ・SALE活用)
日用品や衣類も、工夫次第で無理なく節約できます。
- 雑貨や文房具は100均で揃え、必要があれば他で購入。(まず100均にないか確認するクセができた)
- 服はユニクロ、GU、しまむら、ZOZOのセールを活用。(ユニクロは最近お高めな気がしてますが…)
- ZOZOは、欲しい服はお気に入りに登録しておくと、安くなったタイミングで通知がくる。(クーポン配布もあるので、クーポン期限内かつポイント率の高い日に購入できないかチェック!)
私も子どもや自分の服を、セールやポイントを駆使して購入しています。
おしゃれを我慢せず、でも家計には優しい買い方です。
さらに、着なくなった服をメルカリで売る、というのも年に1〜2回まとめて行っています。
以前、服ではないですが、子どもが大きくなって使わなくなったIKEAのベットも、分解してメルカリで売ったことがありました。安価でしたが大型商品を買ってもらえて嬉しかったです!
通信費の見直し(格安SIM・ahamo・乗り換え体験談)
通信費も家計の大きな固定費です。
我が家では以前、日本通信の激安プランを使っていました。
現在は娘以外はahamoに乗り換えました。少し前に乗り換えキャンペーンでドコモポイント1人2万ポイントもらうことができました。
また、10年近く前は通信費が高かった分、乗り換えキャンペーンの額も大きかったのです。その頃夫婦で乗り換えて、商品券最高9万円分をゲットしたこともありました。しかし乗り換えた後は2年縛りがあったので、2年に一回夫婦でキャリアを変更し、商品券を貯めるというのを何回か実行していました。その時の商品券を貯めておいて、子供たちの制服をデパートで注文しました。
今はそこまでたくさん商品券やポイントがもらえることは無くなりましたが、積極的に乗り換えやキャンペーンをチェックする習慣をつけると家計最適化がぐっと進みます。
住宅ローンの見直し術(繰上げ返済 vs 投資どっちが正解?)
住宅ローンは家計の中でも金額が大きく、見直すだけで将来の負担が大きく変わります。
特に公務員は信用力が高いため、借り換えや金利交渉が通りやすいのが大きな強みです。
まず考えるべきポイント
- 固定金利 or 変動金利の選び方(家庭のリスク許容度が大事)
- 繰上げ返済をするか、投資に回すかの判断基準
- 公務員の信用力を活かした借り換えのコツ
住宅ローンは「どれが正解」ではなく、家庭によってベストが違うのが特徴です。
たとえば、以下のようなタイプで最適解が変わります。
🔸タイプ別の考え方の例
| タイプ | 向いている戦略 |
|---|---|
| 金利上昇が不安・確実に返したい | 固定金利 or 繰上げ返済重視 |
| 教育費が心配・手元資金を厚くしたい | 変動+繰上げ少なめ+現金確保 |
| 資産形成を優先したい | 変動+投資に回す |
「変動が怖い」と言われることもありますが、低金利が続く今の日本では、変動を選んで上手に資金を回す家庭も増えています。



一度、自分がどのタイプなのか考えてみると判断しやすくなります。
我が家の住宅ローン体験談と考え方
我が家は約15年前に変動金利で住宅ローンを組みました。
当初は35年ローンの予定でしたが、「少しでも早く返し終わりたい」という思いから、31年ローンに短縮して契約。
ただし、私は繰上げ返済を急いでいません。理由は3つあります。
✔ 繰上げ返済を急がない理由
- 団信(団体信用生命保険)がある安心感
もしもの時にローンがゼロになる仕組みがあるため、家族への保障としての役割もある。 - 超低金利なので、返すより“増やす”方が合理的
金利1%台が続く中、投資の期待リターン(年3〜5%)の方が上回る可能性が高いため。 - 教育費がかかる時期は“手元資金の厚み”が大事
繰上げに回しすぎて貯金が薄くなるのは避けたい。
私は“借金=悪”ではなく、
「低金利を味方に、家族の安心と資産形成のバランスを取る」考え方をしています。
もちろん、精神的に借金があるのが落ち着かない方は、少額でも繰上げ返済すると気持ちが楽になると思います。
住宅ローンは価値観や教育費スケジュールでも最適解が変わりますが、まずは一度“我が家の場合のベスト”を考えてみるのがおすすめです。
車の維持費を最適化する方法(保険・買い替えタイミング)
子育て家庭にとって車はほぼ必須ですが、維持費が高く家計に重くのしかかります。
買い方や保険の選び方次第で、年間5〜15万円の節約も可能です。
車の維持費を抑えるポイント
- 自動車保険は定期的に見直し(公務員の団体割引なら約10%安くなる場合もあり※要確認)
- 新車・中古車・カーリースのメリットを理解して選ぶ
- 車検・タイヤ・整備費を見込んだ上で総額で考える
我が家の車事情
私は新車は買わない派で、いつも“お買い得な中古車”を探して購入しています。
特に3年落ちくらいの中古車がコスパ最強と感じていて、状態の良いものを見つけた時に決めるようにしています。
今の私の車は、消費税増税後一時期中古車が売れない時期があって、その時に購入したのでかなりお買い得でした。お買い得車をネットで見つけて隣県まで購入しにいきました。
また、地方在住のため、理想は車を1台にしたいところですが、現実的には1人1台ないと生活が成り立たない状況。
そのため、一台一台をできるだけ長く乗る工夫をしつつ、維持費を抑えるようにしています。
車は“お金がかかるもの”と決めつけず、固定費として最適化していく意識が大切です。
教育費とどう向き合う?子持ち公務員のリアル戦略
子どもの教育費は大きな負担ですが、工夫次第で無理なく管理できる部分もあります。
塾や家庭学習の取り入れ方、受験期の考え方まで、実体験をもとに解説します。
塾はフル通塾じゃなくてOKという考え方(スポット利用のコツ)
子どもの教育費は大きな支出ですが、塾にフルで通う必要はないと考えています。
我が家では、成績に問題がなく、本人の通塾希望がなければ普段は家庭学習のみです。しかし、定期的に無料体験や夏期講習などスポット利用で対応しています。定期的に無料体験を行い、夏期講習等のスポット利用も快く行ってくれる塾が近所にあるので助かっています。
子どもと一緒に本屋で参考書を選んだり、家庭学習をサポートすることで、学習効果を高めながら費用を抑えています。下の子は本人の希望で中学受験をしましたが、通塾はせず、自宅学習で私が教えました。
とはいえ、高3・中3の受験期は、受験の情報も必要なので塾に通うようにしています。もちろん受験期の塾費用は高額になりますが、その時期を「教育への投資」と割り切ることで、家計に無理なく対応できます。
家庭学習の工夫(本屋活用&親子で勉強)
家庭学習では、親子で一緒に学ぶことが効果的です。
我が家では、子どもと本屋に行き、成績や興味に合わせて参考書を選ぶ時間を大切にしています。
こうすることで、子ども自身が学ぶ意欲を持ち、塾に頼らずに勉強できる環境が整います。
また、家庭での学習習慣が身につくと、塾費用を節約できるだけでなく、子ども自身の自立学習力も育ちます。
受験期は“投資”と割り切る考え方
中学3年・高校3年など受験期は、どうしても塾費用や教材費が増えます。
ここは「将来への投資」と割り切ることが大切です。
我が家も受験期には一時的に教育費が増えますが、事前にスポット利用や家庭学習で基礎を固めているため、無駄な出費は最小限に抑えられています。



子育て世帯でも、計画的に支出をコントロールすれば、教育費と家計の両立は十分可能です。
無理なく節約しつつ、子どもの学習の質も落とさない戦略が重要です。
子持ち公務員の福利厚生の活かし方(家計に効く節約術)
公務員ならではの福利厚生は、ささやかなものが多いですが活用すれば家計に直接メリットがあります。
レジャーや保険、育児支援など、知っていると得する制度の活用方法をご紹介します。
公務員の福利厚生を家計に活かすべき理由
公務員には給与以外に、“見えない収入”としての福利厚生があります。
例えば、宿泊補助やレジャー割引、育児支援、健康診断、自己啓発補助などです。
こうした制度を使うか使わないかで、生涯で数十万円〜数百万円の差が出ることもあります。
家計最適化を考えるなら、まずはこれらの制度を把握し、積極的に活用することが大切です。
レジャー・旅行・お出かけ費用を節約できる活用術
福利厚生を使うと、家族でのレジャーもお得に楽しめます。
私の場合、毎年秋に家族で梨狩りに参加しています。
普通に行くと少し費用がかかりますが、福利厚生を活用すると安く参加できる程度で済むので、家計に負担なく楽しめます。
梨狩りは子どもたちも大喜びで、毎年の楽しみでした。(今は上の子も高3受験生で梨狩りにはついてこなくなりましたが・・・)
大企業勤めの友人の福利厚生は、ディズニーランドチケット配布など羨ましいものもありますので、公務員だけが特に素晴らしい福利厚生ということは全くないですが、有効活用しない手はありません。
また、自治体によって映画館、水族館などの割引もあり、楽しみながら節約できるのが魅力です。
見落としがちな福利厚生(医療・育児・保険・自己啓発)
福利厚生はレジャーだけでなく、医療費や子育て、保険、自己啓発にも活用できます。
例えば、労働組合経由で加入する車の保険は約10%割引で、家計に優しいです。
これは労働組合費を払っている組合員の団体割引なので、公務員だけでなく他の会社でも使える場合がありますが、知らずに損している人が多いので積極的に活用することをおすすめします。



組合費を節約するために加入しない、という人もいましたが、試算したところ、家族全員分の自動車保険が安くなるため、我が家の場合は組合費を払った方がお得と判断しました。
さらに、出産や育児に関する補助や、資格取得・研修費の支援制度も活用可能です。
私自身、これらの制度を利用することで、家計に無理のない節約と自己成長を両立させてきました。
まとめ
子持ち公務員がFIREを目指すには、安定収入と福利厚生を上手に活用しながら、家計を最適化することが大切です。
本記事で紹介したポイントを整理すると、次の3つが重要です。
- 家計の優先順位を見直す:固定費・変動費・教育費・投資の順で整理
- 日常生活での節約術を取り入れる:食費・日用品・通信費・衣類を無理なく最適化
- 福利厚生や支援制度を活用する:レジャー割引や保険・育児・自己啓発補助など
子育て世帯でも、無理なく実践できる具体例を体験談とともに紹介しました。
少しずつ取り入れることで、家計に余裕が生まれ、FIREに向けた資産形成も進められます。
まずはできることから一つずつ取り組み、自分と家族に合った家計最適化の仕組みを作ることが成功のカギです。



この記事を読んだ方は、今日から小さな節約や制度の活用を始めることで、将来の安心と自由を手に入れる一歩を踏み出せます。