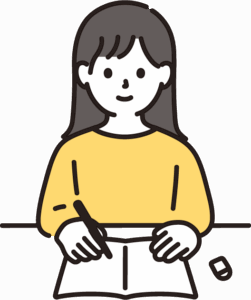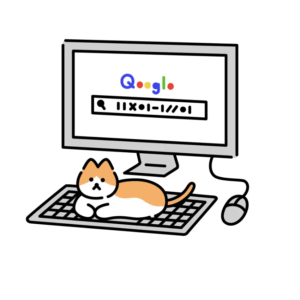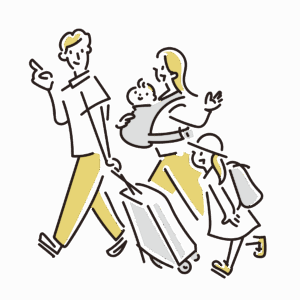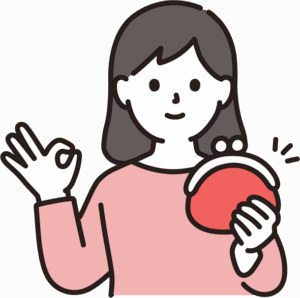「普通の共働き家庭でも、FIREって本当にできるの…?」
「うちの年収・家族構成だと、退職するにはいくら必要なの?」
そんな不安や疑問を抱えていませんか?
本記事では、そんなお悩みを解消します。
✅ 本記事の内容
- 共働き家庭がFIRE・早期退職するために必要な資金の目安
- やってはいけない“退職資金の考え方の落とし穴”
- 共働き家庭でも実現しやすいFIREまでの具体的なロードマップ
✅ 本記事の信頼性
- 子育てをしながら資産形成した実体験をもとに執筆
- FIREまで後1〜2年となった筆者の、資産運用の経験を踏まえた内容
- FIREについて何年も検討を重ねてきた経験
この記事を読むと、あなたの家庭に合わせた「安心して退職できる必要額の目安」がわかり、
“まだ働かないと不安…”という状態から抜け出せます。

「普通の共働き家庭でも、本当にFIREできるの?」と気になっている方は、ぜひ最後までご覧ください。
早期退職後に必要な生活費の目安



FIRE(Financial Independence, Retire Early)とは、
「経済的に自立して早期に仕事を辞める(または働く時間を大幅に減らす)」ことを指します。最近話題ですよね。
FIREに必要な金額は、まず「退職後の生活費」を把握することから始まります。
この前提が曖昧なままでは、必要資金を正しく計算できません。
共働き家庭がFIREを目指す場合、夫婦ふたりなら月22〜28万円の生活費が一般的な目安です。
FIRE後は通勤や外食が減る一方で、医療費や趣味・旅行などが増えるため、現役時代とは使い方が変わります。



ただし、極端な節約生活は長続きしません。
「ムリなく、普通に、ちょっとゆとりもある暮らし」を想定した金額で考えることが大切です。
▼FIRE後の生活費イメージ(夫婦2人)
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 食費 | 6〜7万円 |
| 光熱費・通信費 | 3〜3.5万円 |
| 日用品・雑費 | 1.5〜2万円 |
| 住居費(持ち家) | 1〜2万円(固定資産税・修繕積立) |
| 保険・医療費 | 1.5〜2万円 |
| 車・交通費 | 1.5〜2万円 |
| 趣味・娯楽・旅行 | 5〜7万円 |
| その他 | 2〜3万円 |
| 合計 | 22〜28万円 |
この範囲で生活できる家庭が多く、「ゆとりあるFIRE生活」の現実的なラインと言えます。
あなたの家庭のFIRE後の生活費を算出する方法
必要額は、世帯によって大きく異なります。
だからこそ「平均値」ではなく、あなたの家庭の数値に置き換えることが重要です。
FIRE後の生活費を出すには、次の3ステップで考えると正確になります。
【ステップ1】現状の生活費を把握する
まずは、現在の月間支出を把握しましょう。
家計簿がなくても、次の方法で5分で算出できます。
- 銀行口座やカード明細の1ヶ月分をざっくり合計する
- 生活費だけでなく“隠れコスト”も含める
例:特別費、帰省、家電買い替え、医療費、車検など
年間ベースで把握するとより正確です。
年間支出 ÷ 12ヶ月 = 現在の月平均生活費
【ステップ2】FIRE後に減る支出・増える支出を整理
退職すると多くの支出が変化します。
「現役時代と同じ生活費」で見積もると、必要額を誤ります。
▼ FIRE後に減る可能性が高い支出
- 通勤・外食・飲み会
- スーツ・化粧品など身だしなみコスト
- 教育費(子ども独立後)
▼ FIRE後に増える可能性が高い支出
- 旅行・趣味などゆとり費
- 医療費(年齢とともに増加)
- 住居のメンテナンス費
現役時代の8割〜9割程度で見積もる家庭が多いです。
【ステップ3】“ゆとり費”を必ず上乗せする
ここが抜けていると、FIREが失敗しがちです。
ゆとり費とは、人生を豊かにする支出のこと。
たとえば…
- 旅行・レジャー
- 自己投資(学び、習い事)
- 家族イベント、プレゼント
月3〜7万円は上乗せしておきましょう。
こうして算出した金額が、あなたの家庭のリアルなFIRE後の生活費になります。
例)現状月32万円 → FIRE後は24万円に調整
(減る支出 −8万、増える支出+4万)
FIRE後の月間生活費:24万円 → 年間288万円
1億円で足りる?“安心ライン”と“攻めライン”の必要額比較
「FIREには1億円必要」と言われることもあるようでが、全員にとって1億円が正解とは限りません。生活スタイルや家族構成、どれくらい安心感がほしいかによって“必要額の基準”は変わります。
ここでは、多くの人が気になる「攻め」と「安心」の2つのラインで必要額を比較します。
“攻めライン(最低限)”の必要額:7,000万〜1億円
不安を最小限にしつつ、なるべく早くFIREしたい方向けのラインです。
- 年間生活費を抑える前提(年240〜300万円)
- 教育費は別途確保 or 一部奨学金・バイト想定
- 持ち家で住宅費を抑えられる場合が多い
目安:年間生活費 × 25年分
| 年間生活費 | 必要資産(攻め) |
|---|---|
| 240万円 | 6,000万円 |
| 300万円 | 7,500万円 |
| 360万円 | 9,000万円 |
ミニマルな暮らしや、FIRE後も少し収入を得る予定がある人は、この“攻めライン”でも十分可能です。



ただし、運用利回りや物価上昇に左右されやすく、精神的には少しハードモードになるかもしれません。
“安心ライン(余裕あり)”の必要額:1.2億〜1.6億円
教育費や医療費、想定外の出費にも備え、安心してFIREしたい人向けのラインです。
- 年間生活費360〜420万円
- 教育費や大きな支出も織り込み済み
- 旅行や趣味など「人生の楽しみ」も確保
| 年間生活費 | 必要資産(安心) |
|---|---|
| 360万円 | 約9,000万〜1.2億円 |
| 400万円 | 約1.1〜1.4億円 |
| 450万円 | 約1.3〜1.6億円 |



安心重視なら、多少多めに見積もっておくことで「やっぱり足りなかった…」と後悔しにくくなります。
1億円で足りるかどうかの判断基準
以下に1つでも当てはまる場合、1億円あれば“ほぼ安心寄り”で可能です。
- 持ち家で住宅費が少ない
- FIRE後も月3〜10万円程度の収入を得る予定がある
- 子どもの教育費が既に準備済み or 国公立想定
- 贅沢ではなく、ゆとりがあれば十分満足できる
逆に、次に1つでも当てはまるなら、1億円では足りない可能性が高いです。
- 賃貸で老後も住居費がかかる
- 子どもが私立や留学を希望
- 毎年旅行や娯楽費をしっかり使いたい
- 資産を極力減らしたくないタイプ
まとめ
- 早くFIREしたいなら攻めライン(7,000万〜1億円)
- 不安なく暮らしたいなら安心ライン(1.2〜1.6億円)
- 必要額は家庭の価値観・教育方針・住居形態で大きく変わる
退職・FIREに必要な資産額の計算方法(4%ルールだけに頼らない版)
FIREというと「4%ルール」が有名ですが、私は“そのまま鵜呑みにするのは危険”だと考えています。
理由は、私たちが暮らす日本は物価上昇や増税、社会保険料の負担増など、支出が増える可能性が高いためです。
4%ルールとは、年間支出の25倍の資産があればお金を減らさずに暮らせるという考え方です。
投資しながら、毎年資産の4%だけ取り崩して生活すれば、理論上は資産が長持ちするとされています。



そこでここでは、4%ルールに加え、より現実的で安心できる計算方法を紹介します。
✔️ 基本となる考え方は「必要生活費 × 安全係数」
まずは、あなたがFIRE後に必要な年間生活費を出します。
そのうえで、次の式で必要資産額を求めるのが安心です。
必要資産額 = 年間支出 × 25倍(ゆとりありは28〜30倍)
※25倍=年4%取り崩し
※30倍=年3.3%取り崩し(より安全)
📍 4%ルールだけに頼らない“3段階の安全ライン”
| 安心度 | 年間支出にかける倍率 | 取り崩し率 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 最低ライン(攻め) | 25倍 | 4% | 収入ゼロでもOK!とにかく早くFIREしたい |
| 基本ライン(標準) | 28倍 | 3.5% | 長期的に安心して暮らしたい |
| 安心ライン(守り) | 30倍 | 3.3% | 子どもがいる / 物価上昇が不安 / 長生きリスクを避けたい |
💡 例:年間生活費が360万円の場合の必要資産額
- 攻め:360万円 × 25倍 = 9,000万円
- 標準:360万円 × 28倍 = 1億80万円
- 安心:360万円 × 30倍 = 1億800万円



→ 同じ生活費でも、FIREスタイルで必要額は大きく変わります。
👀 “4%ルールは北米基準”という落とし穴
4%ルールは米国株の長期データが前提。
日本は以下の点で環境が異なります。
- 社会保険料が高い
- 物価上昇が緩やかでも税負担が増えやすい
- 年金制度が複雑で将来調整の可能性あり



そのため、日本では 3.3〜3.5%で考える方が安心 です。
✨ まとめ
- 「年間生活費 × 25〜30倍」で必要額を算出
- 国内FIREは“4%ルールの過信は禁物”
- 子育て世帯は安全係数を上げると安心
教育費と住宅ローンがある家庭の必要額の考え方
教育費や住宅ローンが残っている場合は、単純に生活費×25年だけでは足りません。
これらを考慮した「FIRE後に安心できる資金計画」を立てることが大切です。
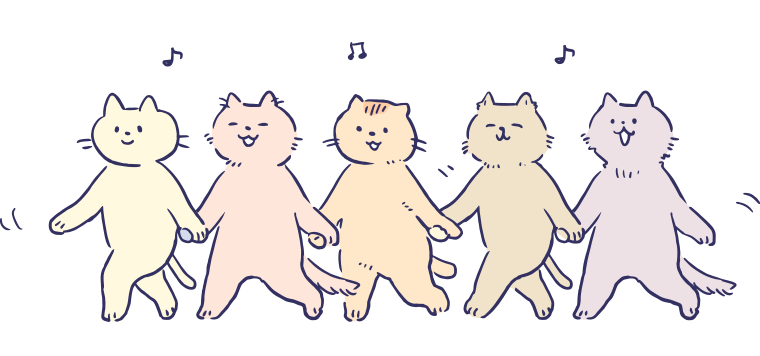
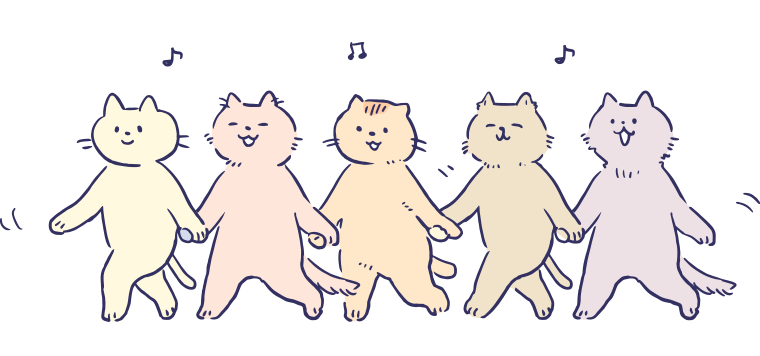
- 教育費:小学校から大学までの総額は、私立・公立で大きく変動。奨学金も選択肢の一つ
- 住宅ローン:ローン残高や金利、返済期間に応じてFIRE資金に上乗せ
- FIRE後の収入:場合によっては、配偶者の収入のみで計算できることもある



教育費を効率的に準備しつつ、ローン返済も無理なく進められる資金設計がポイントです。
FIREで退職するには資産運用が必須
FIREを目指すなら、資産運用は欠かせません。
ただ貯金だけでは、1億円以上の資金を効率的に作るのは難しいです。
積立NISA・iDeCoを活用してFIRE資金を効率的に増やす方法
- 積立NISA:年間40万円まで非課税で長期投資可能
- iDeCo:掛金が所得控除になり、税制メリットが大きい
- 両方活用:長期複利効果で資産を大きく増やせる
公務員でも加入可能な制度をフル活用するのが賢い方法です。
4%ルールと運用利回りの考え方
- 退職後は資産を毎年3〜4%ずつ取り崩す、というのが基本
- 年利3〜4%で運用できれば資産を大きく減らさずに生活可能
- 利回りが低い場合は取り崩し率を下げるか、生活費を調整
運用利回りと生活費のバランスを意識して計画を立てましょう。
資産を減らさないための引き出し戦略
- 必要最小限を生活費に回す:資産の減少を抑える
- ボーナスや臨時収入は取り崩しに含めない:余裕資金として運用
- 長期運用を前提に安全資産とリスク資産を分ける
計画的な取り崩しで、資産寿命を延ばすことが可能です。
不安なく退職するための準備ステップ
FIREを目指すなら、資産運用だけでなく、退職前の準備も重要です。
不安なく生活できるように、具体的なステップを確認していきましょう。


退職前に見直すべき固定費と生活コスト
- 家計の固定費:住宅ローン、保険、光熱費など
- 通信費やサブスクの見直し:無駄を削減して資金を確保
- 生活費のシミュレーション:FIRE後に必要な支出を把握
無駄な支出を減らすことで、必要資産額を下げることができます。
セミリタイアという選択肢:フルFIREとの違いとメリット
- フルFIRE:完全に働かず生活する
- セミリタイア:パートや副業で一部収入を得る
- メリット:資産減少リスクを抑えつつ、生活の自由度を確保
無理のないFIREを目指すなら、セミリタイアも検討すると安心です。
FIRE後の収入源を持つと必要額は大きく下がる
- 副業や投資収益:生活費の一部をカバー
- 年金の活用:受給開始年齢に合わせて生活計画を調整
- 臨時収入のプラン:予期せぬ支出への備え
少額でも継続的な収入があると、FIRE達成に必要な資産を減らせます。
まとめ:退職して後悔しないために必要額を明確にしよう
公務員や安定収入のある家庭でも、FIREを目指すには必要資産の明確化と計画的な準備が不可欠です。
- 生活費の見直し:現役時代とFIRE後で必要な支出を把握
- 資産運用の活用:iDeCoや積立NISAで効率的に資産を増やす
- 退職前の固定費チェック:無駄を減らして必要資産額を抑える
- 収入源の確保:副業や年金を組み合わせてリスクを分散
この記事を参考にすると、FIREに必要な金額や手順が明確になり、安心して退職に踏み切る判断ができます。



FIREを実現して、自由な時間と安心した生活を手に入れたい方は、ぜひこの記事をもとに具体的な資産計画を立ててみてください。