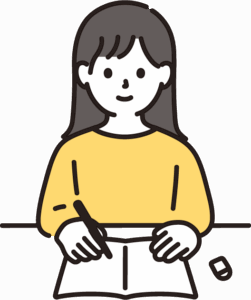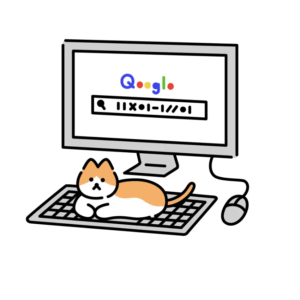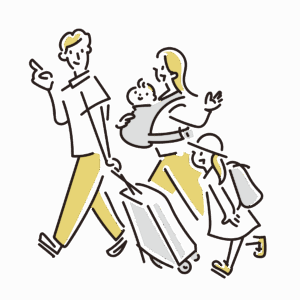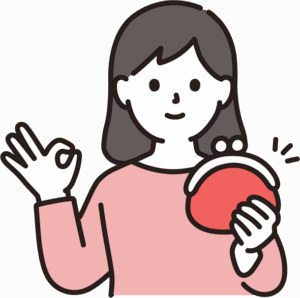子どもの学費も気になるけど、早期退職して自由な時間も手に入れたい…
本記事では、こんなお悩みを解決します。
✅ 本記事の内容
・30代公務員×2人子持ちでも早期退職(FIRE)を目指す具体的な資金戦略
・学費と老後資金を両立する資産形成の優先順位と方法
・退職までの年数別ロードマップと現実的な資産計画の考え方
✅ 本記事の信頼性
・筆者自身、40代公務員・2人子持ちで、15年以上資産運用を続けてきた経験あり
・学資保険で教育費の安心感を確保しつつ、iDeCoやNISAを活用して老後資金・FIRE資金を運用中
・無意識に節約に励む性格で、25歳から余剰資金を投資することで資産が4.5倍程度に
この記事を読むと、学費と老後資金を両立させながら無理なく早期退職を目指す方法がわかるので、安心して資産形成や投資をスタートすることができます。

「投資未経験だけどFIREしたい」「子どもの学費が心配」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
30代公務員×2人子持ちが早期退職するためにまず知るべき前提
公務員が早期退職を考えるタイミングと注意点
「辞めたい」と思うタイミングは、昇任・異動・子育ての節目と重なりがちです。
特に30代後半〜40代前半は、役職の重さや責任が一気に増える一方で、子どもの受験や習い事もピークに。
精神的・体力的な負担から、「このままずっと続けられるのかな?」と感じる人が増えます。



私自身、子どもが小学生と中学生になった頃、
「あと20年以上この生活を続けるのか…?」と将来が急に現実味を帯びてきました。
注意点は、退職金と共済年金の仕組みを理解せずに辞めないこと。
公務員は勤続年数で退職金が大きく変わるため、
“辞めるタイミングの数年の差が数百万円の差”になることもあります。
子どもの学費と老後資金は同時に準備できるのか?



結論から言うと、「できます」。ただし順番が超重要。
特に2人子どもがいる場合、教育費だけで1,000万円〜2,000万円規模になります。
老後資金も同時に準備しようと焦って、リスクの高すぎる投資商品に手を出して失敗したら大変です。
私が育休中に最初に始めたのは投資信託のスポット購入でしたが、復帰後に本格的に積立投資を開始。
学資保険だけでは不足すると感じ、財形貯蓄も解約し投資へ回すなど、優先順位を意識した資産形成に切り替えました。
公務員家庭がFIREを目指す際の3つの現実課題
公務員のFIREには特有のハードルがあります。代表的なのはこの3つ。
- 退職金と年金制度(厚生年金)が“長く勤める前提”で設計されている
→厚生年金は民間企業と同じ。退職金は短期で辞めるほど不利。ただし「辞めどき」は戦略でカバー可能。 - 収入が安定しているため危機感を持ちにくい
→貯蓄できている錯覚に陥りやすい。(私も最初そうでした) - 副業が制限されているため、収入の柱を増やしづらい
→在職中にできる範囲での“資産型収入作り”がカギ。
私は25歳から投資を始めていたことで、早期退職の現実味が急に高まった瞬間がありました。アベノミクス効果で含み益が倍増した時期があったのです。しかしコロナショックで一時は含み損になってしまいました。一度は諦めかけましたが、諦めずに投資を続けた結果「働き方を選べる」状態が見え始めたのです。



次に「実際いくら必要なのか?」を見ていきます。
30代公務員が早期退職するための必要額と資金計画



「2人の子どもがいるのに、本当に早期退職なんてできるの…?」
これは、私自身が一番悩んだテーマでした。
結論からお伝えすると、“完全FIREを目指すか” それとも “ゆるFIRE(少し働く)を選ぶか”によって必要額は大きく変わります。
私は、早期退職後も月に数万円〜10万円ほど働く “ゆるFIRE” を想定したことで、必要額のハードルがグッと下がりました。
ここでは、まず必要額の考え方を整理していきますね。
2人の子どもがいる公務員の早期退職の必要額シミュレーション
早期退職に必要な金額は、以下の3つで決まります。
- 子どもの教育費
- 退職後の生活費
- 老後資金
私自身も、最初は「教育費と老後資金、両方なんて無理…」と思っていました。でも、資産形成を始めて約15年以上経った今、退職目標額の約85〜90%に届くところまで準備できています。
ただし、数字だけにとらわれすぎて焦る必要はありません。
まずは「必要額の全体像」を理解することからでOKです。
子どもの学費はいくら必要?教育費のリアルな総額



子どもの教育費は、公立・私立・文系・理系・下宿の有無で大きく変わります。
我が家の場合は…
- 上の子(公立高校3年):国立大理系を希望→理系私大一人暮らしの可能性を考慮→今後1000万想定
- 下の子(私立中学1年):私立中〜私立高〜私立大理系を希望→今後1500万想定
合計で2500万を想定しています。
正直、教育費は“高め設定”で見積もっておく方が安心です。
一般的な教育費の目安は以下の通りです。
| 進路 | 教育費総額(幼稚園〜大学) |
|---|---|
| すべて公立+大学国立 | 約1,000万円 |
| 公立→私立大学文系 | 約1,500万円 |
| 公立→私立大学理系 | 約1,700万円 |
| 私立中高一貫→私立大理系 | 約2,200〜2,500万円 |
特に私立理系は授業料+実験費用で想像以上にかかります。
「必要額を知る」だけでも、将来の不安が少し軽くなるはずです。
公務員が早期退職後に必要な生活費と老後資金の算出方法
次に、退職後の生活費と老後資金です。
私は、退職後の生活費について以下の2つのパターンで試算しました。
| パターン | 年間生活費 | コメント |
|---|---|---|
| 理想の暮らし | 約500万円 | 年1〜2回の長期旅行含む |
| 少し節約 | 約400万円 | 無理はしないが工夫する暮らし |
そして、老後資金については公務員の場合、以下を踏まえて考えると安心です。
- 共済年金(現在は厚生年金)65歳から支給と想定
- 退職金
- iDeCoや年金保険
※必要資産=教育費不足額+(退職〜年金開始の年間生活費×年数)+(年金開始後の年間生活費×亡くなるまでの年数(想定))−(退職金+既存金融資産+退職後の年収×年数(想定)ゆるFIREの場合)
例えば、私の勤務先の制度で試算した場合、仮に43歳で退職した際の退職金は約1,000万円(あくまで概算です。自治体によって違いがありますので注意!)。
ただし、退職金は「勤続年数で大きく変わる」ので、全員が同じではありません。また、自治体によっては、45歳以上に早期退職制度(退職金上乗せ)を適用できる場合もあるそうなので、よく確認してみてください。
次の章では、「教育費と老後資金を両立できる資産形成の始め方」を、初心者向けにわかりやすくまとめていきますね。



次に「どれから手をつければいいの?」という方に、優先順位付きでご紹介します。
30代公務員×子どもの学費と老後資金を両立する資産形成の始め方
子育て中の公務員が早期退職(FIRE)を目指す場合、限られた収入の中で「学費」「老後資金」「投資による資産形成」をどう両立させるかが最大のテーマになります。
ここでは、私自身が実践してきた方法と、実際に失敗・改善してきた体験談を交えながら、現実的なステップをご紹介します。
まず優先すべき資産形成の順番(学費→老後→投資)
結論からお伝えすると、優先順位は次の3ステップが現実的です。
- 学費の “最低限ライン” を確保する
- 老後資金をiDeCoなどで長期運用
- 残りで投資信託やNISAを活用してFIRE資金を増やす
私自身、まずは子どもの教育費の不安を減らすことを優先しました。
学資保険に加入したのも、「教育費だけは確実に確保しておきたい」という安心感が欲しかったからです。ちなみに子ども2人で合計1200万円を学資保険で準備しました。投資した方がいいのではという思いもありましたが、子どもの学費が一時的にでも目減りしたら、私の場合相当なストレスになるため諦めました。
ただ、学資保険だけではインフレや大学費用の高騰には対応しきれない可能性があります。そこで、教育費の“ベース”だけ学資保険で確保し、追加分は投資信託で積み立てる方法に切り替えました。



このように、「安心の土台+運用による上乗せ」の二段構えが、精神的にも家計的にもバランスが良いと感じています。
公務員に最適な資産運用プラン(NISA・iDeCo・投資信託)
公務員は給与が安定しているからこそ、長期積立型の商品との相性が抜群です。特に次の3つは“セット運用”がおすすめです。
| 制度 | 目的 | メリット |
|---|---|---|
| iDeCo | 老後資金 | 節税+長期運用で効率よく増やせる |
| NISA(つみたて/成長) | FIRE資金づくり | 非課税で投資効率が高い |
| 投資信託+必要に応じて個別株 | 資産の増加スピード強化 | リスクを抑えつつ増やせる |
私が20代のうちは、iDeCoや公務員に可能なNISAの制度もなかったため、ほぼ投資信託のみで資産を増やしていました。その後、30代になり投資信託を一旦辞めて個別株(日本株・米株)のみで運用するようになり、さらに資産が順調に増えていきました。
現在、老後資金はiDeCoで積み立てており、FIRE資金は投資信託と個別株(NISA含む)で“攻め”の運用をしています。
ただ、実は一度失敗もしています。アベノミクス期に相場が好調だった頃、私は“もっと増やしたい”と思って現金比率を減らしすぎてしまいました。
その後の下落局面でうまく買い増しができず、「どんな時も一定のキャッシュは必要」という教訓を得ました。
この経験があってからは、投資資金とは別に、生活防衛費+投資の待機資金をしっかりキープするようにしています。そうすることで、下落直面でも焦らずに買い増しし、株価が戻った頃には資産が増えている、という状況を目指せます。(株価が戻ったら一部を待機資金に戻すことを忘れずに!)
早期退職後も安心な収入源の作り方(副業・配当・在宅ワーク)
資産形成が順調でも、「収入源がゼロになる」のは心理的な不安が大きいものです。早期退職後の安心感を高めるためには、小さく収入を作っておくことが効果的です。公務員に許される副業は範囲が狭いので、「小さい収入を得る準備」をしておくのが良いでしょう。
- 副業(ライティング、事務サポート、オンライン講座など)※在職中注意
- 在宅ワーク(スキル型・事務型どちらも可能)※在職中注意
- 配当収入※在職中も基本的には問題なし
※在職中は副業に制限があるため、所属の規程を確認のうえ、必要な許可・届出を行いましょう。
私はFIRE後は、月10万円程度を在宅で稼ぐ働き方を想定しています。夫の扶養範囲内で働くことを考えていますが、将来的に制度がどう変わるかは分からないので、柔軟に対応できる形にしておくつもりです。
ここだけの話ですが、夫は少し浪費家なところがあり、まだ現在の資産額をしっかり話せていません。
そのため、精神的自立の意味でも「自分自身で収入源を持つこと」は、私にとって大きな安心材料になっています。
この章では「学費・老後・FIRE資金」を同時に準備する現実的な順番と、制度を使った最適な資産形成法をご紹介しました。
次の章では、いよいよ “いつ退職できるのか”が分かるロードマップ を作っていきます。
30代公務員が2人子持ちでも早期退職できる具体的ロードマップ
ここまで、必要額や資産形成のポイントをお伝えしてきました。
「でも、結局いつ・何から始めれば早期退職できるの?」
と思った方に向けて、ここでは年数別のリアルなロードマップをまとめました。
私自身、「子どもが小学生のうちは落ち着いたら考えよう…」と先延ばしにしがちでした。
しかし、42歳の現在振り返ると、もっと早く準備しておけば選択肢は大きく広がっていたと実感しています。



今から始めれば、30代なら十分間に合います。
✅ 5年で早期退職を目指すプラン(攻め×効率重視)
「40代前半で退職したい」「子どもが中学〜高校のうちに自由を取り戻したい」方向け。5年と期間が短いため情勢によっては難しいこともあります。資産目標額が2000万から4000万の方向け。配偶者が働いていれば、ゆるFIREなら可能?というくらいになると思います。
※ゆるFIRE・・・早期退職後も月に数万円〜10万円ほどマイペースに働くこと
特徴:短期集中・支出最適化・投資効率最大化
- 教育費と生活費を徹底管理し、年間貯蓄+投資額を最大化
- NISA・iDeCoをフル活用し、投資比率はやや高めに設定
- 車・保険・通信費の見直しなど、“削れる固定費は短期で削る”
🌱家計見直し最適化の記事は以下をご覧ください。
5年FIREのポイント
| 項目 | 重点ポイント |
|---|---|
| 貯蓄・投資 | 収入の30〜40%を投資へ |
| 投資配分 | 株式比率 70〜80%(長期前提) |
| 子ども | 奨学金・国公立・自宅通学など選択肢整理 |
最もハードだが、最も自由を早く得られるルート。
※投資配分が多くなるため、退職時期に情勢が悪いと資産が一時的に減ってしまう可能性もあるので注意。
🧩 10年でゆとりFIREを目指すプラン(教育費とのバランス型)
「子どもの大学卒業が見えた頃に退職したい」方向け。目標資産が4000万から7000万の方向け。ゆるFIRE、または配当金などで安定的な収入があると安心。
特徴:最も現実的で再現性が高い
- 子どもの教育費と老後資金の両立がしやすい
- 投資リスクを抑えながら資産拡大ができる
- 退職金もある程度増え、年金額にも安心感
10年FIREのポイント
| 項目 | 重点ポイント |
|---|---|
| 貯蓄・投資 | 収入の20〜30%を投資へ |
| 投資配分 | 株式比率 60〜70% |
| 子ども | 大学費用が見通せる時期まで待てるメリット |
最も選択肢が多く、精神的な余裕も確保できる王道ルート。
🌿 15年で安定FIRE(セミリタイア)を目指すプラン(安心重視型)
「老後資金の不安をゼロにして穏やかに退職したい」方向け。目標資産が7000万以上の方向け。配当金などで安定的な収入を得る手段があると安心。
特徴:資産・退職金・年金すべてが安定する
- 子育て終了+教育費確定後に退職できる
- 退職金・年金ともに増える時期まで働く安心ルート
- セミリタイアではなく完全リタイアも現実的
15年FIREのポイント
| 項目 | 重点ポイント |
|---|---|
| 貯蓄・投資 | 収入の15〜20%でOK |
| 投資配分 | 株式比率 50〜60% |
| メリット | 退職金・年金が最大化。安心感が段違い |
最も堅実で、老後まで不安が残りにくいプラン。
⚠️5年・10年・15年のプランを紹介しましたが、投資は元本割れのリスクもあります。退職時にコロナショックのような情勢になる可能性もゼロではありません。ガチホ(買ったら売らない)という考え方もありますが、現金の確保、部分的な利益確定など、資産を守る行動も大切です。
この後は、公務員ならではの「退職金・共済年金を最大限活用する方法」をまとめます。
公務員の退職金・共済年金を最大限活用する方法
早期退職を考えるうえで避けて通れないのが「退職金」と「共済年金」の問題です。
特に30〜40代での早期退職は、金額が大きく変わるため、正確な情報を押さえておくことが重要です。
✅ 退職金は“何歳で辞めるか”で大きく変わる
公務員の退職金は、勤続年数によって増えていきます。
私自身も内規を確認し、仮に45歳で退職した場合は約1,000万円前後になると試算しました。(※あくまで概算)
私は「一度きちんと数字を把握しておこう」と思い、自治体の退職金の内規を調べ、エクセルで試算しました。
正直、「満額まで残らないともったいない」という気持ちが強かったのですが、数字を可視化したことで “満額ではなくても、退職金は大きな原資になる” と前向きに考えられました。
退職金は早期退職の資金として ・ローンの繰上げ返済 ・学費の一部確保 ・投資の元本 のどれに使うかで将来が変わります。



早期退職を考えている方は、まず自分の退職金見込み額を一度シミュレーションしてみるのがおすすめです。
✅ 共済年金は“加入年数がカギ”
公務員の年金は「共済年金(現在は厚生年金に一元化)」ですが、加入年数によって受給額が変わります。
早期退職すると、その後は国民年金に切り替わるため、厚生年金だけの人より年金額が減りやすい点に注意が必要。
私は試算したところ、
退職後は夫の扶養に入り国民年金に切り替えた場合、将来の年金受給額は年約140万円ほどになる試算でした。
公的年金は自分で計算しようとするととても複雑で、最初は「もう考えたくない…」と思ったほど(笑)
でも、実際に数字を知ることで、「老後までにあといくら準備すべきか」が明確になり、むしろ気持ちがラクになりました。



▼年金見込み額は、以下の厚労省公式ツールで簡単に試算できます
https://nenkin-shisan.mhlw.go.jp/
✨ 退職金×年金を最大化する3つのポイント
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| ① 定年まで残る場合・途中退職する場合の退職金を比較 | ざっくりでも良いので「何歳退職ならいくらか」を把握 |
| ② 年金受給額をシミュレーション | 国民年金切替後どう変わるか確認 |
| ③ 足りない部分を投資で補う | 不足額=毎月の投資目安が決まる |
退職金と年金は、早期退職を考える公務員にとって、最大級の意思決定ポイントです。
「もらえる金額」ではなく「どう活かすか」で、FIRE成功率は大きく変わります。
子育てと早期退職を両立するマネープラン成功事例
私自身、42歳で2人の子どもを抱えながら、公務員として働きつつ資産運用に取り組んできました。上の子は国立大志望(受験生)、下の子は私立中学から内部進学で高校、その後私立理系大学希望で、学費の負担は大きく、資産形成と生活費のバランスが重要となっています。
以下は、私が実際に実践している資金計画の一例です。
| 項目 | 方法・内容 | 月額/年間 | コメント |
|---|---|---|---|
| 教育費(学資保険) | 上の子・下の子の学資保険で最低限の教育費を確保 | 月2〜3万円程度ボーナス払いもあり | 教育費の安心感を確保しつつ、投資への精神的余裕を作る |
| 老後資金(iDeCo) | インデックス型中心で運用 | 公務員は月2万円が限度 | 退職後の年金を補完、節税メリットも享受 |
| 投資(NISA・投資信託・個別株) | リスクを取りつつ資産形成 | 月5〜10万円 | 現金ポジションを残しつつ、積極的に運用。過去の失敗から学んだ現金確保の重要性も反映 |
| 生活費見直し | 不要な支出削減、通信費乗り換え | 年間数万円節約 | 小さな節約でも複利効果で資産形成を後押し |
| FIRE準備 | 退職目標額の85〜90%達成を目安に積立 | – | 教育費・生活費・老後資金のバランスを考慮し現実的な目標設定 |
この表の計画に沿って、私は「学資保険で教育費の最低限を確保」「iDeCoで老後資金を積み立て」「投資でFIRE資金を攻める」という二段構えの戦略を取りました。特に現金ポジションは、過去のアベノミクス期後のコロナショックの反省から、急な相場下落でも対応できるよう余裕を持たせています。
30代公務員の方におすすめしたいのは、まず「教育費の最低限確保」と「生活費の見直し」をしながら、少しずつ投資を始めることです。これにより、無理なくFIREを目指す資金計画を作ることができます。
まとめ:30代公務員×2人子持ちでも早期退職を目指せる
この記事では、30代公務員で2人子持ちの方が、子どもの学費と老後資金を両立しながら早期退職(FIRE)を目指す方法を解説しました。
ポイントを整理すると:
- 30代のうちに早期退職の前提を理解しておく
公務員ならではの退職金・年金制度や、学費・生活費の現実的な必要額を把握することが第一歩です。 - 30代のうちに資産形成の順番と具体策を明確にする
学資保険で教育費の安心感を確保し、iDeCo・NISA・投資信託で老後資金・FIRE資金を計画的に増やすことが重要です。 - 30代から現実的なロードマップを描く
5年〜15年の退職目標別に、生活費・学費・投資戦略・副収入などを組み合わせて具体的なマネープランを作ると、迷わず行動できます。
まだ時間のある30代のうちから早めに実践することで、無理なく子どもの学費と老後資金を両立しながら、早期退職を目指せます。



この記事を今読んでいるあなたなら、早期退職の目標を達成することができるでしょう!